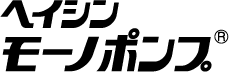技術コラム IoT・AIで変わる
IoT・AIで変わる
「送る&運ぶ」
さまざまな産業において始まりつつある、IoT化、AI(人工知能)活用。
移送・搬送の現場への影響や技術トレンドについて、電子・機械系雑誌のジャーナリストであるエンライト代表:伊藤元昭氏がわかりやすく解説します。
第19回
再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは
生産計画に沿って工場を円滑に操業するうえで、電力の安定調達は重要な要素です。日本では当たり前だと考えられがちですが、世界に視野を広げれば、日本ほど恵まれた電力事情の国や地域は少ないと言えます。
しかし近年、カーボンニュートラル達成に向けた取り組みの中で、製造業を取り巻く電力事情が一変しつつあります。工場に電力を供給するシステムが再生エネルギー(再エネ)主軸型へと変わることで、必要な時に、安定的かつ低コストで、潤沢な電力を調達することが難しくなる可能性があるのです(図1)。電力の利活用には、利用する需要家側にも相応の工夫が求められるようになり、日本も例外ではありません。
今回は、近未来の工場を取り巻く電力事情と課題を、IoTやAIなどICTの活用効果を交えながら解説します。

再エネ主軸の電力システム、大口需要家に求められるマインドチェンジ
カーボンニュートラル達成に向けて、発電から送配電、蓄電、活用に至る社会全体の電力システムを大きく改造しようとする動き(GX、グリーントランスフォーメーション)が進められています。最も大きな変化は、電力を生み出す際のエネルギー源の主軸を、火力から太陽光や風力などの再生可能エネルギーへ移行することです。
海外では、CO2を排出しない原子力を主軸にする動きもありますが、東日本大震災の記憶が鮮明な日本では、再エネを優先することになりそうです。2023年2月に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」でも、再エネを主力電源化していくことが明記され、さまざまな施策が打ち出されています。
主力電源の再エネへの移行は、電力を作り、供給する電力会社だけの課題ではありません。実は、最も大きな変化が求められるのは、製造業をはじめとする電力の大口事業家です。いかなる形の電力システムであっても、「同時等量の原則」という大原則に基づいて運用する必要があります(図2)。同時等量の原則とは、需要量と供給量を常に同じになるように制御することを求める運用法であり、この原則を守らないと大規模停電などが起きてしまうからです。

火力発電の場合には、投入する燃料の量を調整すれば発電量を制御できます。ところが、自然現象を利用する再エネでは、ある程度は蓄電設備などでやり繰りできるものの、基本的には供給量を調整することができません。このため、需要側に需要と供給のバランスを維持するための協力が求められるのです。
このように、工場での一層の省エネ努力が必要になるとともに、電力の供給状況に合わせた工業製品の生産調整が求められる可能性が高まってきています。
再エネ対応の操業に向けたスマートファクトリーとは
どんな製造業であっても、例外なく、製品の生産性を高めるための努力をしています。再エネの活用を推し進めるために省電力化や生産調整が求められたとしても、それによって生産性が低下するのは、本音では苦しいところでしょう。それでも、大量の電力を利用することが許されなくなる時代はやってきています。対策として、生産現場に潜む無駄な電力消費をきめ細かく見つけて削減する「省電力志向のスマートファクトリー技術」、供給に余裕のあるときに電力を溜めておき、必要になったタイミングで利用するための「蓄電設備」、自社工場への「再エネの発電設備」などの導入が必要になってきます。
これらの新たな設備を効果的かつ効率的に活用するためには、ICT(情報通信技術)の活用が有効です。現場での装置・設備の稼働状況をリアルタイムで把握するためのIoT、生産計画や電力需要の変動、気象状況などを鑑みた再エネでの発電量を予測するためのAIの活用に期待が集まっています。
省電力志向のFAシステムや産業用発電蓄電設備が続々投入
 こうした時代の到来を鑑みて、ここ1、2年、省電力志向のスマートファクトリー技術が、FAシステムなどを開発・供給している企業にとっての重要な訴求ポイントになりつつあります。現在、工場でのIoT活用は、省電力化やCO2の削減効果を最大化させるための改善点を洗い出す目的を持つものが増えてきています。
こうした時代の到来を鑑みて、ここ1、2年、省電力志向のスマートファクトリー技術が、FAシステムなどを開発・供給している企業にとっての重要な訴求ポイントになりつつあります。現在、工場でのIoT活用は、省電力化やCO2の削減効果を最大化させるための改善点を洗い出す目的を持つものが増えてきています。
たとえば、同じ製品を同じ量だけ生産したとしても、生産する時間帯や時期をズラしただけで、再エネの活用割合が高まる可能性があります。こうした点も考慮に入れながら、再エネ中心の電力システムへの適応を支援するICTシステムも提案されています。ほかにも、装置の動きを減速する際のエネルギーを電力として回生して再利用するサーボドライブ装置なども商品化されました。
また、工場に太陽光発電設備や蓄電設備を導入する企業も増えました。電力機器を開発・提供するメーカー各社は、工場への導入を想定した大出力の太陽光パネルや大容量のバッテリー・エネルギー貯蔵システム(BESS)の品揃えを強化しています。海外では、比較的長時間にわたる工場内での電力需要を調整するため、太陽光をエネルギー源とした水素製造装置と燃料電池を組み合わせた蓄電システムを導入しているところもあります。これらの設備の導入効果を最大化するためには、工場内での電力消費量と発電量をリアルタイムで正確に把握し、AIを使って先読みしながら、蓄電設備の充放電を適性制御することが求められます。
いち早く再エネ対応投資を実施する企業が得する制度設計
ここまで動向の解説を読んでいただいた方の中には、「再エネを主軸とした電力システム導入の重要性はわかるが、なぜ製造業各社が新たな設備投資をしなければならないのか。これは、日本のものづくりの強みを後退させる施策なのでは」と感じる人もいるかもしれません。こうした声を見越してか、政府は、再エネ対応の設備投資を推し進める企業には相応の経営上のメリットが出るように制度設計しています。
「GX実現に向けた基本方針」では、官民合わせて今後10年間で150兆円を超えるGX対応の設備投資を目標に掲げています。需要側への投資の産業部門別内訳を見ると、素材が約8兆円以上、自動車・蓄電池が約34兆円以上、脱炭素目的のデジタル投資が約12兆円以上、ゼロエミッション船舶が約3兆円以上投じられる見通しです。
これらの産業部門でGX対応の設備投資をする場合には、補助金などの拠出や各種優遇策が提供されるということです。逆に、需要量が極大化するようなタイミングで多くの電力を調達した場合には、相応の追加コストを支払う必要が出てくる電気料金の設定になる可能性も見込まれます。
また、大口需要家である工場が、電力需要量の減少に協力すれば、その企業にインセンティブが働く仕組みの導入が計画されています。
具体例を挙げます。政府は、「GX経済移行債」と呼ばれる国債の発行を開始し、今後10年間で20兆円規模の先行投資支援を見込んでいます。積極的に先行投資してGXの成果を上げた企業には、負担が小さくなるように、逆に投資が遅れれば、CO2を大量排出することによるペナルティー的な負担が課されることになると思われます。投資を先行させ、負担はカーボンプライシング、要するに事業で排出するCO2の量に応じて後から課して回収する仕組みです。
設備導入の支援や導入後の投資回収を支援する新たな仕組み
工場への太陽光パネルや風力発電設備の設置は、製造業の企業が自ら導入することもできますが、PPA(Power Purchase Agreement)の仕組みを使って、無償で導入することも可能です(図3)。

PPAとは、企業などが保有する施設の屋根や遊休地を事業者が借り、無償で発電設備を設置し、発電した電気を企業・自治体が施設で使うことで、電気料金とCO2排出を削減する仕組みです。設備そのものは第三者(事業者または別の出資者)であるエネルギーサービス会社が所有する形となるので、資産保有することなく再エネの利用比率を高めることができます。既にPPAサービスを提供する企業も複数あり、活用できる体制が整ってきています。
さらに、需要側で保有しているエネルギー資源(コ・ジェネレーション、蓄電池、電気自動車、ネガワットなど)を電力システムに活用する仕組みの構築も進められています(図4)。工場で保有する分散型エネルギー資源一つ一つは小規模ですが、IoTを活用した高度なエネルギーマネージメント技術によって、これらを束ね(アグリゲーション)、遠隔・統合制御することで電力の需給バランスの調整に活用できます。こうした仕組みは、あたかも一つの発電所のように機能することから、「仮想発電所(Virtual Power Plant:VPP)」と呼ばれています。

ここで挙げたネガワット(節電した電力)とは、需要を意図的に減らすことで、他者が使う電力の余力を生み出すことを指します。需要制御の仕組みには、電力料金設定によって電力需要を制御する「電気料金型」や電力会社やアグリゲーターなどと需要家が契約を結び、需要家が要請に応じて電力需要の制御などを行う「インセンティブ型」の2種類があります。既にVPPのアグリゲーターも国内に存在し、着実に利用実績を増やしています。
まとめ
社会インフラが充実している日本では、蛇口を回せば水が出て、コンセントにプラグを挿せば電気が使え、バルブを開けばガスが使えることが当たり前と、多くの人が考えています。そんな日本だからこそ、新たな時代の到来を見据えてマインドチェンジする必要があります。電力の調達に逼迫してから対策するのではなく、他社に先んじて対策を講じてみてはいかがでしょうか。
2024年5月公開
- PROFILE
 伊藤 元昭氏
伊藤 元昭氏
株式会社 エンライト 代表- 技術者として3年間の半導体開発、日経マイクロデバイスや日経エレクトロニクス、日経BP半導体リサーチなどの記者・デスク・編集長として12年間のジャーナリスト活動、コンサルタントとして6年間のメーカー事業支援活動などを経て、2014年に独立して株式会社 エンライトを設立。
NEXT
-
 ポンプの
ポンプの
基礎知識クラス
移送に関する基本情報を
わかりやすくコンパクトに
解説していきます。- 【A-1a】ポンプの種類
- 【A-1b】ポンプの種類(容積式ポンプ)
- 【A-2】ポンプの原理
- 【A-3a】軸封装置
- 【A-3b】軸封装置(メカニカルシール)
- 【A-3c】軸封装置(グランドパッキン)
- 【A-4a】NPSH(Ⅰ)
- 【A-4b】NPSH(Ⅱ)
- 【A-5】ウォーターハンマー
- 【A-6a】ポンプ選定時に確認すべき事項(1)
- 【A-6b】ポンプ選定時に確認すべき事項(2)
- 【A-6c】ポンプ選定時に確認すべき事項(3)
- 【A-7a】ポンプに使用される金属材料について
- 【A-7b】ステンレス鋼について
- 【A-7c】ステンレス鋼の腐食形態について
- 【A-7d】ポンプに使用される非鉄金属について
- 【A-8a】ポンプに使用されるゴム材料について
- 【A-8b】ゴム材料の物理的な特性
- 【A-8c】ゴム材料の化学的な特性
- 【A-9a】金属材料への表面処理
-
 ポンプの
ポンプの
周辺知識クラス
規格や周辺機器情報などを
解説していきます。- 【B-1a】ポンプの洗浄1
- 【B-1b】ポンプの洗浄2(自動洗浄における洗浄効果の因子)
- 【B-1c】ポンプの洗浄3(SIPとASEPTIC)
- 【B-2a】駆動機(駆動機の概要)
- 【B-2b】駆動機(三相交流かご形誘導モーター)
- 【B-2c】駆動機(保護方式と耐熱クラス)
- 【B-2d】駆動機(モーター技術の動向)
- 【B-2e】駆動機(変速装置・減速装置)
- 【B-2f】駆動機(番外編:周波数)
- 【B-3a】インバーターの基礎知識(Ⅰ)
- 【B-3b】インバーターの基礎知識(Ⅱ)
- 【B-3c】インバーターの基礎知識(Ⅲ)
- 【B-3d】インバーターの基礎知識(Ⅳ)
- 【B-3e】インバーターの基礎知識(Ⅴ)
- 【B-3f】インバーターの基礎知識(Ⅵ)
- 【B-4】防爆
- 【B-5】管材と計測器
- 【B-6】トップランナーモーター
- 【B-7】マグネットカップリング
-
 移送物の
移送物の
基礎知識クラス
液の特長や性状および
主な用途などを
解説していきます。 -
 IoT・AIで変わる
IoT・AIで変わる
「送る&運ぶ」
移送・搬送の現場がIoT化、
AI(人工知能)活用で
どのように変わるのか。
伊藤元昭氏が解説します。- 第1回:産業機器のIoT化で何が変わるか
- 第2回:IoTは、日本のものづくり企業こそ活用すべき
- 第3回:AI活用の本質は、匠の技やベテランの知恵の機械化
- 第4回:AI活用を円滑・効果的に進めるための鍵は現場力にあり
- 第5回:AIの「ブラックボックス問題」との付き合い方
- 第6回:5Gで加速する工場・プラントでのIoT活用
- 第7回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?①
- 第8回:ものづくりのDXで、現場の仕事はどう変わるのか?②
- 第9回:協働ロボットで作る、人と機械が助け合う現場
- 第10回:コロナ禍で加速した、ものづくりでのAI/IoT活用
- 第11回:IoT/AIを駆使して対応する脱炭素時代のものづくり
- 第12回:製造業での脱炭素化、最初に始めたいこととは
- 第13回:サプライチェーンの管理は見える化から自律化へ
- 第14回:パブリックな仮想世界、メタバースは製造業に何をもたらすのか
- 第15回:メタバース上のバーチャルファクトリーで、多方面の専門家が密に協業
- 第16回:リチウムイオン二次電池から全固体電池へ、実現の鍵を握る技術「MI」
- 第17回:電極・電解質・イオン種、全方位で進化し続ける二次電池
- 第18回:スマホや自動運転車の技術転用で、産業機器や働くクルマの自律化を実現
- 第19回:再エネ主力電源化時代が到来、大口需要家である工場に求められる備えとは
-
 現場の声で、
現場の声で、
ひとくふう
モーノポンプの使い方は現場によりさまざま。
ひとくふうを加えると、
実はおもしろい発見が!